コンテンツへスキップ
今回は
デッキの床板が傷んで
きたので見て欲しい
というご相談を頂きました。
※
今回の別荘は、
デッキの上に
屋根があります。

ですので
確認してみても
傷みがあるのは
先っぽの数枚だけで
他はキレイな状態。

根太がどれだけ
傷んでいるかは
剥いでみないと
わかりませんが
※
板が一束もあれば
足りそうな感じ。
※
そこでいつも通り
あらかじめ板を
加工し塗装もして
交換作業に入ります。
※
板を剥いで根太の
状態を確認します↓

※

傷みが来ている
部分もありますが

※

※

下の大引が支えている
部分が広いので
この程度なら
持ちそうです。

そこで板を張り付け

※

仕上げの塗装をして
完成です!

※

これでまたしばらくは
安心ですね。
※
ではまた~♪
※
もっと建築工事・ウッドデッキ工事を見る
TOPページに戻る
ウッドデッキが
傷んできたので今度は
コンクリートテラスと
※
雨が当たらず
痛みにくい軒下に
ウッドデッキを造りたい
※
というご相談を頂きました。

ウッドデッキはともかく
コンクリートテラスは
源さんの出番です。

さっそく解体して
型枠&砕石工事
に入ります。

特に西側は
段差が高くなるので
型枠も転圧も十分に
行う必要があります。

しっかり砕石が
転圧できましたら
今度はコンクリートを打ちます。
※
そして型枠を外すと・・・↓

なかなか見事な
コンクリートの豆腐が!

ご要望頂いた目地に
カラー砕石も映えて
バッチリです!

源さんの担当分が
終わったので今度は
私の出番です。
※
せっかく源さんが
コンクリートテラスを
キレイに造ったので
塗料で汚したくありません。
※
そこでいつも通り
あらかじめ木材を塗装し
あとは組んで固定すれば
良い様に準備しておきます。
※
そして一気に
組み上げます↓

今までのご相談頂いた
修理の経験から
※
箱階段にすると
どうしても隅の
水切れが悪く
そこから傷みやすい
※
という事がわかり
きっているので
こんな形の階段にします↓

これで(箱階段よりは)
多少は長持ちする”はず”です。
※
デッキ床板も設置したら
(どうしても必要な)
仕上げの塗装に入ります。
※
キレイに保ちたいので
しっかり養生をして

乾いたら養生を
外して完了です。


薪もデッキ下に入れたい
※
というご希望にも
適いますし
これで快適に
お使えいただけるかと。
※
ではまた~♪
※
もっと建築工事・ウッドデッキ工事を見る
もっと土木・伐採工事を見る
TOPページに戻る
今回はウッドデッキの
修理のご相談です。

ウッドデッキが
傷んでいて危険なので
※
夏までに安心して
使える様にしたい
※
というご希望でした。

下から確認してみると

なかなかの
傷みっぷりです。

そこで修理の工事を
させて頂きます。
※
まずは傷んだ部分の
解体作業に入ります。

板や傷んだ根太・大引
を取り外します。

柱や板の木工事に
入る前にまずは
材料の塗装です。

防腐剤注入材に
ステイン塗料を
たっぷり塗り込みます。

そして
大引・根太掛けの
掛ける部分も事前に
彫り込んで準備しておきます。

あとは運び込んで
一気に施工します。

※

最後に
仕上げの塗装
をして終了です。

※

※

これで夏に安心して
お使いいただけます。
※
ではまた~♪
※
もっと建築工事・ウッドデッキ工事を見る
TOPページに戻る
今回は以前、
※
建物南側に
デッキ通路&屋根掛け
※
をご依頼頂いた
お客様よりのご相談です。
※
※前回の工事の様子↓

西側にある
既存デッキにも
屋根を掛けて欲しい
というご要望でした。

※

そこで
屋根掛けの工事
に入ります。
※
まずはいつも通り
材料を最初に塗装します。

※

そして
塗装した材料を
トラックに積んで運びます。

柱を建てて
桁を据え付け↓

垂木掛けを
取り付け↓

垂木と桟木を
取り付けます。

次はケラバ
(屋根端部)に
金物を取り付けます。

そして
屋根材を葺く前に
ここでもう一度
仕上げの塗装をします。

塗装が乾いたら
屋根を葺きます。

今回は
お客様のご希望で
”オパール”
という色の
ポリカ波板を葺きます。

この色は
ホームセンターや
金物屋さんや
工具店には
置いていない色です。
※
そして完成です↓

※

※

※

お客様には
※
期待通りの物が出来た様で
感謝いたします。
※
快適に過ごせる様になり
喜んでおります。
※
というご感想を頂けました。
※
こちらこそ嬉しいです!
※
ではまた~♪
※
もっと建築工事・ウッドデッキ工事を見る
TOPページに戻る
物置が雨漏りする
というご相談を頂きました。
※
屋根に上ってみると
典型的な
雨漏りパターンの
アスファルトシングル葺き。

しかもなかなかの
劣化状態。

屋根の上に防水紙も
丸出しで破れ
野地板丸出し↓

しかも屋根の片方は
既に垂木まで
傷んでしまい
凹んで苔まで生えている↓

これじゃ雨漏りしても
当然と言えば当然。
※
完全に直すには
屋根と垂木を取り外し
※
桁を確認してから
造り直す必要があります。
※
※
ですが、
そこまで費用を
掛けられない
との事でしたので
※
現状の屋根の上に
そのまま重ね葺き
することになりました。
※
※
まずは屋根の上の
剥がれた
アスファルトシングル
を掃除します。

そして防水紙を
敷きながら↓

桟木を取り付けて
固定していきます。

今回は下地の垂木が
どこまで強度が
残っているのか?
※
イマイチ信用
できないので
桟木同士も固定していきます。

防水下地と桟木を
取り付け終わったら
(写真にはありませんが)
※
屋根端部の金具を
取り付け下地の木材が
表に出ないようにします。
※
そして
ガルバリウム波板を
葺いていきます。

※

※

※
全部葺いたところで
今度は棟カバーを
取り付けていきます。
※
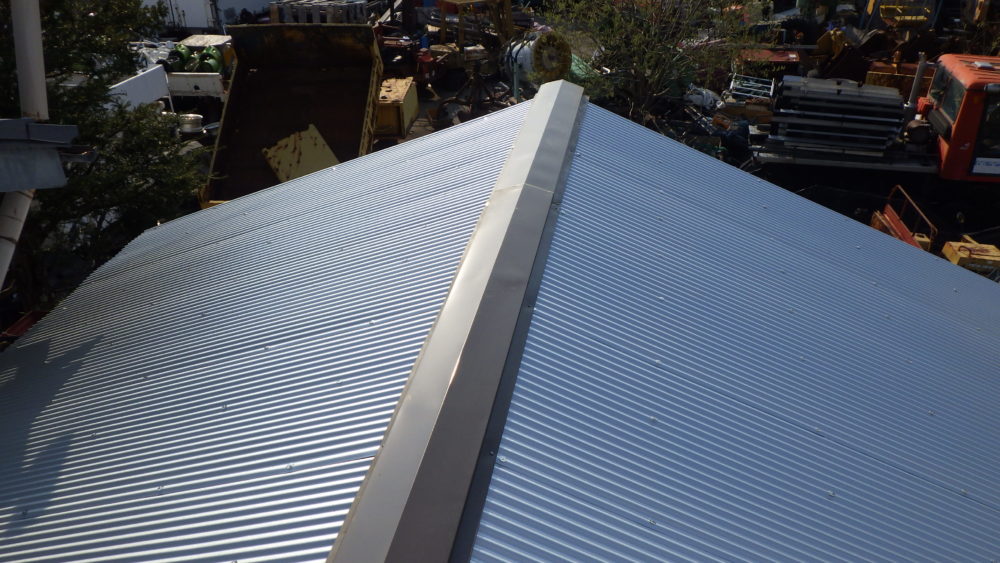
最後に雨仕舞を
確認しながら
隙間等にキレイに
シリコンを打って終了です。
※
この切り込んだ
屋根の取り合い部分に
特に気を使いました。

これでとりあえず
雨漏りも止まって
お客様も一安心されていました。
※
良かったです~
※
ではまた~♪
※
もっと建築工事・ウッドデッキ工事を見る
TOPに戻る
※
スキーが好きな
別荘オーナー様より
※
スキー道具を持ったまま
冬でも安心して歩ける
デッキが欲しい
※
というご相談を頂き
デッキ工事です。
※
現状ですと一旦
この坂を下ってから↓

階段を再び上がって
玄関へという順路。

冬にスキー板を担いだまま
凍った坂を下りてから
上るにはちょっと大変です。
※
そこでデッキを造って通路にします↓

※

そして屋根を掛けます。
※
桁の上に垂木と桟木を掛けて↓

ちなみに手摺の形状は
お客様のこだわりの
デザインです。

屋根を葺く前にしっかり塗装します。

ちょっとした事なのですが
仕上がりと屋根の持ちが違います。

そして屋根を葺きます。
今回はポリカ波板で葺きます。

※

最後に仕上げで
塗装の傷みやすい
デッキ面や
※
目につく部分などを
塗っていきます。

※

※

これで雪が降った日でも
スキー板を担いだまま
快適に玄関まで
移動できます。
※
※
お客様には
※
素晴らしいものを
作って頂き
ありがとうございました。
※
見るのが楽しみです。
※
と言って頂き光栄です♪
※
ではまた~♪
※
もっと建築工事・ウッドデッキ工事を見る
TOPページに戻る
物置に使っていた
貨車倉庫の雨漏りを
何とできない?
※
というご相談を頂きました。

ということで
まずは屋根に上って
調べてみます。

おお~

これはなかなか・・・
※
コーキングのシリコンが
紫外線による劣化で
ダメになったのか?
※
それとも
板金がダメになったのか・・・
※
どちらかでしょうが
いずれにせよ雨漏り箇所の
特定は難しそうです。
※
さらに、仮に
シリコン打ちや塗装で
一旦は雨漏りが止まっても
数年後にはまた
雨漏りが発生しそうな気が・・・
※
※
そこでお客様と相談の上
貨車倉庫の上に
ポリカ波板の屋根を
造ることになりました。
※
まずは材料の塗装です。

一般的に普通の大工さんは
工事前に材料への
塗装はしません。
※
完成してから木部の
塗れる部分だけ塗装をする
というのが通常です。
※
ですが、完成してから
塗装するとなると
どうしても塗装しきれない
部分があります。
※
それじゃ残念なので
当方ではできるだけ
最初に塗装します。
※
※できない場合もありますけど
えへへ(〃´∪`〃)ゞ

塗装が乾いたら
屋根の設置作業です。
※
まずは既存の雨どいを外します。

これは後で使うので
壊さない様に慎重に外します。
※
雨を外側に流したいので
勾配をつけられるように
片側を高くします。

そこに垂木を掛けていき

垂木の途中でも
垂れない様に
調整の材木を下に
入れていきます。

そしてその垂木の上に
桟木を設置して
下地は完了!

完成した屋根下地の上に
ポリカ波板を
打ち付けていきます。

屋根葺きは完成。

屋根の端に出てしまう
桟木の切り口を
(できるだけ)
濡らしたくないので

けらばに隅金物の
板金を取り付けます。
※
そして近くの水路に
雨水が流せるよう
勾配を考えながら
雨どいを着けていきます。

最初に取り外しておいた
雨どいを取り付けて完成です!

これで雨漏りの
再発の心配もないし
安心していただけました。
※
ではまた~♪
※
もっと建築工事・ウッドデッキ工事を見る
TOPに戻る
今回は知り合いの方より
床がフワフワしている
ので見て欲しい
とご相談を頂きました。

最初、経年劣化で木が痩せ
それが原因で畳を踏んだら
※
少し下がった様な感じ
がするのだろうな、と
そう予想していました。
※
しかし、実際に床下を開けて
見てみると驚愕。
※
原因はシロアリでした。

結局、和室の床下は
全部交換が必要になり
床下のやり直しの
工事に入ります。
※
まずは床を全部撤去します。

そして、大引き・根太を設置します。

再びシロアリにやられない様
また今の主流でもあるので
束は木ではなく鋼製束を使います。
※
そしてキレイに床板を張り上げ


最後に畳を戻して終了です。

お客様から
いろいろありがとう!
というお言※葉とともに
カレーライスをご馳走頂き
※
帰りの道中食べてね!
※
ということで
カレーパンとコーラを
お土産に頂いちゃいました。
※
こちらこそ御馳走様でした!
※
お役に立て光栄です。
※
ではまた~♪
※
もっと建築工事・ウッドデッキ工事を見る
TOPページに戻る
当方が独立当初
からのお客様より
※
板葺きが数枚剥がれて
飛んで行ってしまった。
※
この際、屋根を葺き直したい
※
とのご相談を頂きました。

現状は↑こんな感じの
板葺き屋根で、
おっしゃる通り屋根板が
数枚飛んで無くなっていました。
※
もし、
一文字葺きや瓦棒引き
などの板金工事で行うのなら
※
専門の板金業者さんに
依頼する必要があります。
※
一文字葺き↓

板金横葺き↓

ですが打合わせの中で、
オンデュリンクラシックシート
で施工した事例を参考までに
お伝えさせて頂いた処

別荘オーナー様が、
※
30年経ったら私も
この世にいるかわからない
からこれで良いよ
※
と仰りオンデュリンでの
施工が決まりました。
※
どうして
富士見のお祖母ちゃん
といい
そんな寂しい発言をするの?
※
人間は120歳まで生きれる様に
できているので
それまで頑張って下さい・・・
※
と、こういった言葉を
聞く度に思いますが
そこまでは立ち入れない話です。
※
話しはさておき工事に入ります。
※
まずは仮設足場を組みます。
※
防水紙
(アスファルトルーフィング)
を敷きながら、
桟木を打って行きます。

今回は薪ストーブの
煙突があるので
その周りは特に念入りに
雨仕舞していきます。

※

ちなみに足場についてですが
今回は少々苦労しちゃいました。

玄関前の部分のスロープが
ガラス屋根になっており
※
足場屋さんも嫌がって
施工してくれなかったのです。
※
ですからこちらで工夫が
必要になりました。
※
↓こんな感じに恐怖のガラス屋根が・・・

割っちゃったらホント恐怖!
※
そしてその西側はこんな感じ↓に窓で一杯。

こちらも割りでもしたら大変です。
※
そこで↓こんな風に足場板を
渡して臨時の足場を
作りながらの作業です。

※

ちなみに↑この方は
忙しい時に手伝ってくれる
大工さん。
※
40年以上の大工経験があり
とても頼りになります。
※
話しは戻って、
以前オーナー様より
※
ついでに煙突の掃除
もしちゃってね
※
というご希望を
伺っていたので序でに
煙突掃除もしちゃいます。
※
煙突の頭を外すと・・・

なかなか見事な汚れっぷり♪

これをブラシでゴシゴシ!!

奥の奥までゴシゴシ!!

細かなススがムワーンとしてきます。
※
それでも汚れはしっかり落とせました。

ストーブの方を確認すると↓
 はい、結構落ちています。
はい、結構落ちています。
※
これを全部きれいに
掃除機で掃除して

※

※

はい、煙突掃除完了!!

さて、屋根に戻って
雨仕舞いの続きです。
※
棟カバーを取り付けられる様
下地の桟木を取り付けながら

棟部分の雨仕舞をして
オンデュリンクラシックシート
を取り付けていきます。


天窓部分の雨仕舞は
特に気を使います↓

※

煙突廻りも
綺麗に出来ました。

そして全部葺き終えて、
屋根の葺き替えは完了!

最後に足場を撤去し
工事完了!

※

※

完成した様子を
別荘オーナー様に
見て頂いた処
※
もっと倉庫っぽく
なるかと思ったけど
※
思ったよりキレイに
仕上がっていて良かった!
とお言葉を頂けました。
※
ふ~良かった~~♪
(^。^;)ホッ
※
ちなみに煙突掃除はお仕事を
頂いたのでサービスです。
※
ではまた~♪
※
もっと建築工事・ウッドデッキ工事を見る
TOPページに戻る
以前お仕事を頂きました
別荘オーナー様より
薪小屋を造って欲しい
というご相談を頂きました。
※
どうもJマート富士見店で
(※現綿半の富士見店)
売っていた薪小屋を
イメージされていた様です。

ただ出来合いの物を
置くだけならこの値段でも
できるのですが、
※
・草刈り機を入れる納屋が欲しい
※
・草刈機の長さは2mなのでそれが入る大きさで
※
・薪小屋の外回りを板張りにして欲しい
※
・棚板を付けて欲しい
※
・砕石をしっかり敷いて欲しい
etc
※
のご希望がお有りでしたので
当方へご相談頂けた様です。
※
※
ということで
先ずは基礎作りです。
※
設置する場所を全体的に
木の根っこだらけの土を掘り↓

砕石を入れます。↓

砕石を均し
コンクリート束石を
設置しコンクリートを巻きます↓

そして再び砕石を
しっかり入れて
基礎工事は完了です。

Jマート富士見店さんで
見たのは2×4の材料で
ビス止めで造ってありました。
※
2×4も金具を正しく
使って造ればしっかりした
強度の物ができます。
※
ですが、
ビスで止めるだけの
仕上がりなら
在来工法のホゾ差しの方が
圧倒的に強度が出ます。
※
ホゾでの組み立て式ですから
そのままで十分強度があって
当然です。
※
という訳で今回は
ホゾ差しで施工させて
いただきました。
※
こんな感じ↓

え?
いきなりその場面!?
と思われた方。
※
はい!
いつも通り作業に熱中していたら
写真を撮り忘れました!
(・ω・ノ)ノヒョエ~
※
この段階でシッカリと塗装をして↓

屋根にポリカ波板を葺きます↓

薪を乾燥させる為に、
ある程度壁板に
隙間を空け壁板を取り付けます。

中に棚も設置して↓

物置も使用できるようにします↓

棚板が無いと
一度に薪を積んだら
下側の薪はなかなか
取り出せません。

しかし棚板があると
上の段と下の段の薪を
好きな様に取り出せます。
※
一冬で薪小屋ひとつ分の薪を
全部使用するのでしたら
関係ない話ですが、
※
そうで無い場合は棚板が
あった方が便利です。
※
今回の別荘では、
週末使い
という事でしたので
棚板を付けさせて頂きました。
※
ともあれ全部の塗装も
終わって完成です↓

最後にサービスで、
他の現場で玉切りした木が
あったのでプレゼントです♪

薪ストーブに入る大きさなら
太いままでも良いですし、
※
寝る前に太い薪をくべて
空気の量を絞っておけば
朝まで温かですしね~♪
※
これで寒い冬も暖かく
お過ごしいただければ
と思います。
※
もっと建築工事・ウッドデッキ工事を見る
TOPページに戻る


































































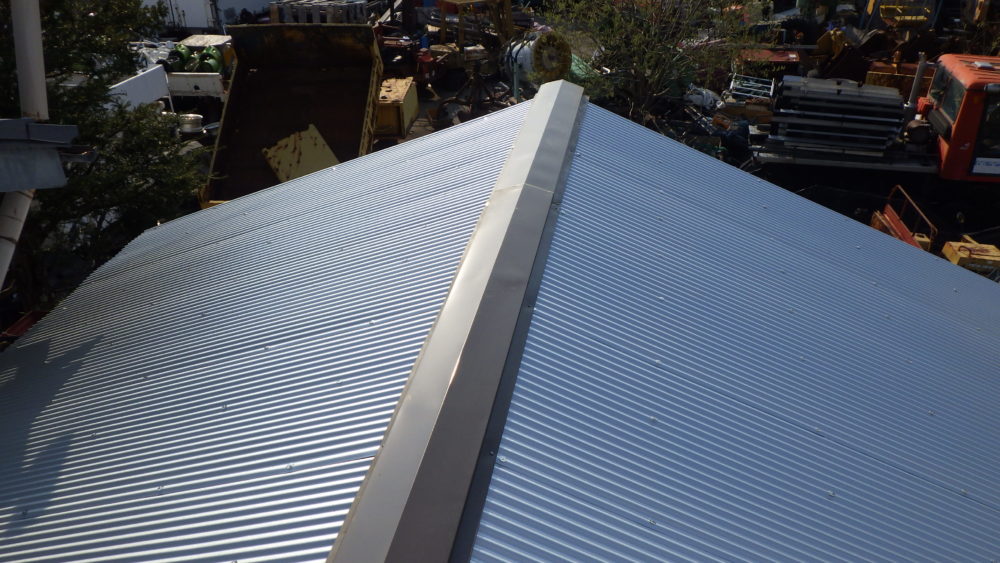





















































 はい、結構落ちています。
はい、結構落ちています。


























